「剣道を始めたいけど、何から手をつければいいのか分からない…」
「基本の動作がうまくできない…」
「試合で勝てるようになりたい!」
「昇段審査に向けた準備とは?」
この記事を読んでいるということは、剣道初心者としてどこから何を始めればいいのか分からないという悩みを抱えているのではないでしょうか?同じ話でも先生によって言う事が違ったり、ネット情報ではいまいちイメージがつかめなかったりしますよね?
そんなあなたのために!今回剣道の基本から上達までの完全ガイドをお届けします。この記事を最後まで読めば、剣道の基礎知識や練習方法、試合での勝ち方や昇段審査まで、理解が深まります。さらに、剣道の達人キャラクター(剣道の達人キャラクター:剣豪先生 剣道初心者キャラクター:若葉くん)を設定し、初心者にアドバイスを提供する形式でお伝えします。ぜひ参考にしてください!
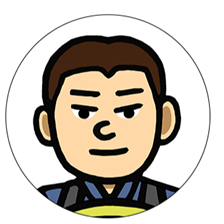


これだけは知っておいて!剣道の基本ガイド
①剣道とは何か
②初心者に必要な装備
③基本的な技と姿勢
④剣道の礼儀作法
⑤継続するためのコツ
⑥筆者の体験談


若葉くん、剣道は基本をしっかり学ぶことが大切だよ。まずは、これだけは知っておいてほしいことを教えるね!

お願いします、剣豪先生!

まずは、剣道とは何かから始めよう。剣道は日本の伝統的な武道で、竹刀を使って技を競い合うんだ。心技体の調和を目指し、精神的な成長も大切にする武道なんだよ。

なるほど、心技体の調和が大事なんですね!

次に、初心者に必要な装備について説明するよ。竹刀は竹製の剣で、稽古や試合で使うんだ。道着と袴は剣道専用の服装で、動きやすさと防護を兼ね備えているんだ。そして、防具は面(頭)、小手(手首)、胴(胸)、垂(腰)を守るんだ。

わあ、まるで本物の剣士みたいですね!早く防具をつけて稽古したいです!

基本的な技と姿勢も重要だよ。足さばきは前後左右の動きをスムーズに行う技術、打ち込みは正確に相手を打つ技術、構えは攻撃と防御の準備姿勢なんだ。

基本をしっかり身につけることが大事なんですね!

剣道の礼儀作法も基本として忘れちゃいけないよ。剣道が試合の勝ち負けだけではなく、先生や仲間に対する敬意を忘れずに、稽古を通じて礼儀を身につけよう。社会人になったときにもこれは役に立つよ。

なるほど、剣道で礼儀作法を学ぶことで、人間形成にも繋がるんですね!

最後に、継続するためのコツを教えるよ。定期的な稽古を続けることで上達するし、自分の目標を設定してそれに向かって努力することが大事なんだ。例えば、剣道初段の取得を目指すとか、目標とする選手や先輩を決めて技を盗み、自分の技にしていく喜びが継続のモチベーションになるんだ。

目標を持って頑張ります!
剣道の基本ガイドとして大まかに、「剣道とは何か」「初心者に必要な装備」「基本的な技と姿勢」「剣道の礼儀作法」「継続するためのコツ」の5つに分けて説明します。
まずは、これらの基本をしっかり理解することで、その後に紹介する具体的な練習方法や上達のコツへの理解も深まり、効果が高まります。そのため、まずは基本についても読んでみてください!「早く技術を習得したい!」という人は流し読みでも構いません! ちょっと目を通すだけでも、これからの稽古への取り組み方が変わってきますよ!ぜひ、参考にしてみてくださいね!(^^)!
剣道とは何か
剣道は、日本の伝統的な武道で、竹刀を使って技を競い合います。心技体の調和を目指し、精神的な成長も大切にする武道です。
初心者に必要な装備
竹刀 : 竹製の剣で、稽古や試合で使用。
道着・袴: 剣道専用の服装で、動きやすさと防護を兼ね備えています。
防具 : 面(頭)、小手(手首)、胴(胸)、垂(腰)を守ります。
基本的な技と姿勢
足さばき: 前後左右の動きをスムーズに行う技術。
打ち込み: 正確に相手を打つ技術。
構え : 攻撃と防御の準備姿勢。
剣道の礼儀作法
礼儀は剣道の基本。先生や仲間に対する敬意を忘れずに、稽古を通じて礼儀を身につけます。
継続するためのコツ
定期的な稽古: 継続的に練習することで上達します。
目標を持つ : 自分の目標を設定し、それに向かって努力しましょう。例えば、剣道初段の取得を目指すなど。また、「●●選手のようになりたい」と目標とする選手や先輩を決めて
技を盗み、自分の技にしていく喜びが継続のモチベーションになっていきます。
筆者の体験談
剣道の稽古の終わりに「姿勢を正して黙想―!」と背筋を伸ばして黙想をし、稽古を終えるということをみんなで毎回やっていました。私が剣道を始めたばかりの頃、先生に「剣道をすると姿勢が良くなると言われるのは、稽古中に背筋を伸ばすことをやるからだ」と言われました。その甲斐あって、今勤務している会社でも「姿勢が良いですね」と言われます。
礼の仕方の参考動画はこちら▼
【警視庁公式チャンネル 少年剣道基本けいこ(入門編1)】より引用
早く教えてほしかった!剣道の基本動作と技術
①足さばき
②打ち込み
③構え
④礼儀作法
⑤継続練習
⑥筆者の体験談


剣豪先生、剣道を始めたばかりなんですが、基本動作と技術をマスターするためのポイントを教えてください!

もちろんだよ、若葉くん。まずは足さばきだ。これは剣道の基本中の基本で、前後左右の動きをスムーズに行う技術だよ。足さばきを早くマスターすることで、他の技術の習得もスムーズになるんだ。

足さばきが大事なんですね!次に何を練習すればいいですか?

次に打ち込みだ。正確に相手を打つ技術で、これも基本的な動作の一つだよ。練習の中で何度も打ち込みを意識することで、自然に身についてくるんだ。

打ち込みも重要なんですね!他には?

そして構えだ。攻撃と防御の準備姿勢で、しっかりとした構えができていないと、他の技術も上手くいかないんだ。正しい構えを身につけよう。

構えも大切なんですね!礼儀作法についても教えてください。

礼儀作法も忘れちゃいけないよ。剣道は礼儀を重んじる武道だから、先生や仲間に対する敬意を忘れずに、稽古を通じて礼儀を身につけよう。

礼儀も大事なんですね!最後に何かアドバイスはありますか?

最後に継続練習だ。定期的な稽古を続けることで上達するし、自分の目標を設定してそれに向かって努力することが大事なんだ。例えば、剣道初段の取得を目指すとか、目標とする選手や先輩を決めて技を盗み、自分の技にしていく喜びが継続のモチベーションになるんだ。

目標を持って頑張ります!ありがとうございます!
剣道を始めたばかりのあなたへ、基本動作と技術をマスターするための5つのポイントをご紹介します!特に初心者にとって重要なのは、「足さばき」です。この技術を早くマスターすることで、他の技術の習得もスムーズになります。練習の中で何度も足さばきを意識することで、自然に身についてくるでしょう。剣道初心者の大人も、このポイントを押さえておきましょう。
すり足
前後左右の動きをスムーズにする基本技術。すり足という足さばきがしっかりできることで、攻撃や防御がより効果的になります。剣道初心者あるあるですが、足さばきに苦戦する人が多いです。
打ち込み
面、小手、胴を正確に打つ技術。正確な打ち込みは、剣道1本を取るための鍵 となります。
構え
攻撃と防御の準備姿勢。正しい構えができることで、安定した動きが可能になりま す。これは、剣道初心者の基本です。
礼儀作法
剣道の基本となる礼儀。稽古前後の礼儀を守ることで、心を鍛えることができ ます。礼儀は剣道初心者の大会でも重要です。
継続練習
定期的な稽古の重要性。継続的な練習が、技術の向上につながります。下記の3でお伝えする基本練習メニューをもとに、繰り返し練習しましょう。
筆者の体験談
私が始めたころ、道着や防具は付けずに私服で①のすり足の練習をメインにやっていました。先生がここに練習時間の多くを割いていた理由がわからず「ひょっとしたら私の足で道場の床の掃き掃除をさせているのかな?」と思ったりしました。(笑)しかし、ここが一番の基本として重要だということは後で分かりました。
すり足の参考動画はこちら▼
【@KendoJidaiInternational Kendo Basics【FOOTWORK】Kouda Kunihide 8th Dan // 基本動作【足さばき】香田郡秀八段 ・ 剣道授業】より引用
初心者のための練習方法を解説!
①構え
②すり足
③打ち技
④礼儀
⑤継続は力なり
⑥筆者の体験談

上記2を踏まえ剣道初心者が知っておきたい、基本動作と技術を5つのポイントにまとめました!
構え
- 右足と左足の間をにぎりこぶし一つ分ひらき、右足のかかとがを左足のつま先のつけねあたりまで前に出します。
- 構えの確認: 正しい構えを3分間維持する練習。鏡を使って自分の構えの姿勢を確認します。まず自分の竹刀が鏡に映った自分の喉に向かってむくように剣先の高さを合わせてください。
すり足
前進・後退: 10分間、2歩前進と2歩後退の動きを繰り返す練習。姿勢と足の動きをチェックしながら行います。地味な練習ですが剣道のいろはのいとなります。
打ち技
- 前後素振り: 面への打突を仮定して、前進して振り下ろす(1回)、後退して振り下ろす(1回)を30回行います。自分の体の中心線を竹刀が通ることを意識しながら行います。
- 跳躍素振り: 跳躍前進して振り下ろす→後退して振りあげる(1回)を30回行います。上記と同じく自分の体の中心線を竹刀が通ることを意識しながら行います。
- 打ち込み: パートナーがいれば、パートナーに自分の竹刀を方の高さで横向きにもってもらい、それに打突をする打ち込み練習をします。
礼儀
礼の練習: 稽古の開始と終了時に必ず礼を行い、礼儀を徹底します。
目標設定
練習記録をつけ、毎日の目標を設定します。小さな目標を達成することでモチ ベーションを維持します。
筆者の体験談
私の通っていた道場ではグリッド付き全身鏡があり、素振りの練習もその線を見ながらまっすぐに振り上げ、振り下ろしができているかチェックしながらやっていました。初心者は右手に力が入りやすく、その結果右斜めに打つ悪い癖がついてしまうことがよくあります。鏡を見て練習することは合理的な練習です。
素振りの参考動画はこちら▼
【夫婦剣道 【剣道】素振り紹介(基礎・初心者向け)】より引用
剣道具の正しい選び方と使い方とは?
①竹刀の選び方
②防具の選び方
③道着と袴の選び方
④剣道具の使い方
⑤剣道具のメンテナンス
⑥筆者の体験談


剣豪先生、剣道具の正しい選び方と使い方について教えてくださ
い!

もちろんだよ、若葉くん。まずは竹刀の選び方から始めよう。竹刀は小・中・高・大・社会人で長さと重さに決まりがあるのを知っているかな?

そうなんですか、自由に自分で決めていいわけではないんですね?

次に防具の選び方だ。防具は面、小手、胴、垂の4つがあるんだけど、それぞれのサイズやフィット感が重要なんだ。特に面は頭にしっかりフィットするものを選ぼう。

防具は自分に合ったものを選ぶんですね!

道着と袴の選び方も大事だよ。道着は動きやすさと通気性がポイントで、袴は腰にしっかりフィットするものを選ぼう。これで動きやすくなるよ。

わあ、道着と袴を着たら、まるで本物の剣士みたいにかっこよくなれそうですね!早く着てみたいです!

剣道具の使い方も覚えておこう。竹刀の持ち方や防具の着け方を正しく学ぶことで、怪我を防ぎ、効果的に稽古ができるんだ。

貼付け使い方もちゃんと覚えます!

最後に剣道具のメンテナンスだ。竹刀は定期的にチェックして割れやささくれがないか確認し、防具は汗をかいたらしっかり乾かし時には洗って清潔に保とう。これで長く使えるよ。

メンテナンスも大事なんですね!ありがとうございます、剣豪先
生!
剣道初心者の方へ、剣道具の選び方と使い方について詳しく解説します!
竹刀の選び方
- 素材と長さ:
小学生: 3.0~3.6尺(約91~111cm)
中学生: 3.7尺(約114cm)
高校生: 3.8尺(約117cm)
一般(大学生・大人): 3.9尺(約120cm) - 重さ:
中学生: 男子440g以上、女子400g以上
高校生: 男子480g以上、女子420g以上
一般(大学生・大人): 男子510g以上、女子440g以上 - 太さ:
中学生: 男子25mm以上、女子24mm以上
高校生: 男子26mm以上、女子25mm以上
一般(大学生・大人): 男子26mm以上、女子25mm以上 - 買える場所: スポーツ用品店、オンラインショップ
- おすすめ: 竹刀専門店の製品
- 費用感: 2,000円~5,000円
- リンク: 竹刀の購入はこちら▶ 剣道 竹刀の通販価格と最安値
防具の選び方
- 面(めん): フィット感が重です。試着して頭にしっかりとフィットするものを選びます。
- 小手(こて): 柔らかく動かしやすいものを選びます。試着して手首の動きがスムーズか
どうか、フィット感を確認します。 - 胴(どう): 軽量でフィット感が良いものを選びます。試着して胴ひもを結んだとき窮屈
にならないか確認した方が良いです。。 - 垂(たれ): 動きやすさを確保するために、軽量で柔軟性のある垂を選ぶと良いでしょう。上記の胴と合わせて試着してフィット感があるか確認しましょう。
- 買える場所: 剣道具専門店、オンラインショップ
- おすすめ: 高品質な防具セット
- 費用感: 30,000円~100,000円
- リンク: 防具の購入はこちら▶ 【楽天市場】剣道武道具(スポーツ・アウトドア)の通販
道着と袴の選び方:
- 道着: 綿素材が一般的ですが、ポリエステルなどの動きやすい素材もあります。初心者に はシンプルで洗いやすいものがおすすめです。
- 袴: 丈が合ったものを選びましょう。身長に合った長さで、動きやすさと見た目のバランスが取れたものを選びます。長すぎると稽古中に自分の袴を自分で踏んで転倒することがあります。
- 買える場所: 剣道具専門店、オンラインショップ
- おすすめ: 初心者向けの道着と袴セット
- 費用感: 5,000円~15,000円
- リンク: 道着と袴の購入はこちら▶ 剣道着・剣道袴のことなら、剣道具専門店の剣道屋
剣道具の使い方
- 竹刀の握り方: 左手でしっかりと握り、右手は力をいれず添えて持つイメージです。打ち 込み時の安定感を高めます。特に左手は小指に力をいれて握ります。練習によって手にできる「まめ」は右手よりも左手にまめができるのが良いと言われます。
- 防具の着け方: 面、小手、胴、垂を正しく装着し、安全性を確保します。ひもはしっかり 結びましょう。しっかり結ばず、試合中に面ひもや胴ひも(特に下の方のひも)がほどけた為に、試合をいったん中断して結び直すケースが見られますが、そのような事がないように注意しましょう。
剣道具のメンテナンス
- 定期的な点検: 剣道具の状態を確認し、必要に応じて修理や交換を行います。特に竹刀の 状態には注意が必要で、特に剣先にささくれがないか毎回チェックしましょう。ささくれは伸びると稽古や試合中に相手をケガをさせる危険なものです。ささくれがあれば、竹刀削り、ヤスリ、竹刀 オイルを購入して必ず手入れをしましょう。
- 清掃と保管: 使用後は防具を乾燥させ、風通しの良い場所で保管します。清潔を保つこと で、道具の寿命を延ばします。
- 剣道具のメンテナンス用品を探す
筆者の体験談
私の場合は道場で貸出をしているもので練習してきましたが、かなり古く、面の頭上の部分が剝げて薄くなり、打突を受けたときに衝撃が強く、耳鳴りがするようになりました。もし頭上が剥げている場合は、パットなどで補強をして頭への衝撃を減らすようにしましょう。
昇段審査をパスしよう!
①剣道の昇段審査の一般的な内容
②日本語剣道形(にほんけんどうかた)の練習方法
③練習スケジュール例
④試合形式の練習方法
⑤学科試験対策
⑥筆者の体験談


剣豪先生、昇段審査に合格するためにはどうすればいいですか?

若葉くん、昇段審査に合格するためには、準備と計画が重要だよ。まずは審査の内容を知っておこう。基本的な技術や日本剣道形の演武が求められるんだ。

日本剣道形とはなんですか?

日本剣道形とは、真剣を使うことを想定しながら剣道の稽古をするために編み出された形稽古のことだよ。木刀を使い、打太刀(うちたち)と仕太刀(しだち)という二つの役割があるんだ。

形の練習はどのように進めればいいですか?

まず基本の動きをしっかりと覚えよう。そして、相手との呼吸を合わせることが大切だよ。形の中には、剣道に必要な動きがすべて含まれているんだ。間合いや剣線の高さ、相手の呼吸を理解することができるんだよ。

実技試験では何を意識すればいいですか?

実技試験は試合形式だけど、勝つことよりも基本に忠実な打突や姿勢、足さばきを評価されるんだ。一足一刀の間合いから正確に打突を繰り出すことを意識して、相手に打たれても気にせずに臨もう。

学科試験対策はどうすればいいですか?

学科試験対策も忘れちゃいけないよ。昇段審査では、実技だけでな く学科試験もあるんだ。剣道の歴史や基本的なルール、礼儀作法についてしっかりと勉強しておこう。練習スケジュールを立てることも重要だよ。計画的に練習を進めることで、効率よく技術を向上させることができるんだ。
剣道の昇段審査に向けた準備や練習方法について、初心者でも分かりやすく解説します。この記事を読んで、昇段審査に自信を持って臨みましょう。
剣道の昇段審査の一般的な内容
- 日本剣道形(けんどうかた) 概要: 形を通じて基本技の正確さや姿勢を評価されます。 内容: 剣道形は剣道の基本技を見せるもので、指定された形をペアで演じます。「木刀による形」が行われます。
- 実技試験 概要: 実技試験では、基本的な打ち技や足さばき、構えの技術が試されます。 内容: 実技には「基本技」と「試合形式」が含まれます。基本技では、基本に則ったの 打ち込みや足さばきが評価され、試合形式では相手との実際の対戦を通じて技術が見られます。
- 筆記試験(段位により実施) 概要: 剣道の目的や心構え、構えの姿勢、礼儀作法、足さばき、試合の心構えなどについての問題が出題されます。
- 目的: 受験者が剣道の精神や技術を正しく理解しているかどうかを評価します。
日本剣道形(かた)演武の練習方法
- 基本の習得
形の理解: 形の動作を教本や動画を見て、イメージを掴み、体が自然と覚えるくらい何度でも自分で やってみましょう。その上で、動作の意味を理解する方が意味が理解しやすいです。
形のパターン:形は攻める側と受ける側の2パターンの役割を演じなければなりません。 攻める側を「打太刀(うちだち)」、受ける側を「仕太刀(しだち)」と言います。
指導者の指導: 指導者や上級者から直接指導を受けることで、誤った動作があれば修正を
学びます。また疑問点はその場で解決しましょう。 - 繰り返し練習
ペア練習: 形はペアで行うため、パートナーと一緒に練習します。お互いに動きを確認し 合い、正確に演じることを目指します。
反復練習: パターンを変えて何度も繰り返し練習します。これにより、動作が自然に体に染み付いています。 - 礼儀作法の徹底
挨拶と礼: 形の前後には正しい挨拶と礼を行います。礼儀作法は形の一部として重要視さ れるため、丁寧に行うことが大切です。
精神集中: 形の演技中は集中力を切らさず、一つ一つの動作に心を込めます。 - 模擬審査
模擬試験: 実際の昇段審査と同じ環境で模擬審査を行います。緊張感を持って本番さなが らの練習を行うことで、当日の不安を軽減できます。
フィードバック: 指導者やパートナーからフィードバックを受け、改善点を見つけます。 指摘された点はすぐに修正しましょう。
練習スケジュール例
- 週3回の剣道形のペア練習: パートナーと週3回、形の練習を行います。各回30分から1時間程度が目安です。
- 毎日の個人練習: 個人練習として、毎日15分程度、形の動きを復習します。特に難しいと
- 感じる部分を重点的に練習します。
- 月1回の模擬試験: 月に一度は模擬審査を実施し、進捗を確認します。本番に備えた練習 を積み重ねることが大切です。
- 実技試験の形式は試合形式ですが、基本に沿った打突や姿勢、足さばきができているかを 評価する事が目的です。したがって試合に勝とう!、勝とう!という気持ではなく、一足 一刀の間合いから正確に打突を繰り出すことを意識して臨みましょう。相手に打たれても 一向に構いません。
試合形式の練習方法
- 模擬試合の実施
定期的な模擬試合: 週に1回は模擬試合を行い、本番さながらの練習を行います。試合形 式での動きや戦術を身につけます。
反省と改善: 模擬試合の後はビデオを撮ることができればそれを見直し、改善点を確認します。指導者やパートナーからのフィードバックを活用しましょう。 - 礼儀作法の徹底
礼儀の練習: 稽古の始めと終わりに必ず礼を行います。正しい礼儀作法を習得し、審査でも自然に行えるようにします。
学科試験対策
- 過去問の活用:過去の試験問題を解くことで、出題傾向を把握し、実際の試験に備えるこ とができます。過去問を繰り返し解くことで、知識の定着を図りましょう。
- 基本的な知識の習得:剣道の歴史や基本的な技術、礼儀作法についての書籍や資料を読み、理解を深めましょう。特に、試験で出題される可能性のあるテーマについて重点的に 学びます。
筆者の体験談
日本剣道形は木刀を使いますので間違えたら相手に木刀があたってケガさせるのでは?とひやひやした記憶があります。
自分が打太刀、仕太刀のどちらになってもいいように繰り返し練習して本番に「あれっ?次は何をするんだっけ?」とならないようにしましょう。
日本剣道形の参考動画はこちら▼
【全日本剣道連盟 日本剣道形(日本語版)】より引用
試合で勝ちたい!
①基本の練習を繰り返して体に染み込ませる
②強豪チームの試合観戦と技を盗む
③試合形式の実践:
④練習試合を多くこなす
⑤筆者の体験談


剣豪先生、試合で勝つためにはどうすればいいですか?

若葉くん、試合で勝つためには、基本の練習を繰り返して体に染み込ませることが大切だよ。特に竹刀の動きで中心線を外さないことを意識しよう。

基本の練習をしっかりやるんですね。でも、試合で緊張してしまうん
です。どうしたらいいですか?

貼付け場数をこなして慣れることだね。また強豪チームの試合を観戦して技を盗むことも重要だよ。彼らの技術や戦術を学び、自分のプレイに取り入れることで、技術をさらに磨くことができるんだ。技術を磨けば、試合に対する自信も変わってくるよ

強豪チームの試合を観戦するんですね!でも、実際の試合でどう動け
ばいいか分からないです。

リハーサルとして試合形式の練習をしよう。実際の試合を想定して模擬試合を行うことで、試合中のプレッシャーや緊張感に慣れ、冷静に対応する力を養うことができるんだ。

試合形式の練習もするんですね!でも、実際の試合でうまくいくか
な?

練習試合を多くこなすことも重要だよ。試合経験を積むことで、異なる剣風に対する対応力が身につき、どんな相手でも冷静に対処できるようになるんだ。

練習試合も大事なんですね!ありがとうございます、剣豪先生!
試合で勝つためには、日々の練習や試合経験が重要です。以下のポイントを押さえて、技術を向上させ、試合での勝利を目指しましょう。
基本の練習を繰り返して体に染み込ませる
2でお伝えした基本練習を日々しっかり取り組みましょう。特に練習時には竹刀の動きで中心線を外さない事を常に意識しましょう。
強豪チームの試合観戦と技を盗む
公式試合で自分のチームが敗れた場合、すぐに自宅に帰るのではなく、準決勝や決勝に進出した強豪チームの試合を観戦することをお勧めします。これにより、彼らの技術や戦術を学び、自分のプレイに取り入れることができます。強豪チームの試合を観戦することで、技を盗むことができ、その技を自分のものとすべく明日からの練習に取り入れて、技術をさらに磨いていきましょう
試合形式の実践
実際に試合で想定される場面、例えば自分が一本を先に取られた場面、自分が一本を先に取った場面と仮定してどう試合を進めるかを意識して模擬試合するなどしてみましょう。これにより、試合中のプレッシャーや緊張感に慣れ、冷静に対応する力を養うことができます。また、試合形式の練習を通じて、自分の弱点や改善点を見つけることができるため、次の試合に向けて効果的な対策を立てることができます。
練習試合を多くこなす
試合で勝つためには試合そのものに慣れることも大事です。試合は様々なチームと対戦します。基本が同じでも道場によっては剣風(道場や流派特有のスタイルや雰囲気を指します)が違うことがあります。剣風が違っても雰囲気におされることなく試合に慣れることが重要です。試合経験を積むことで、異なる剣風に対する対応力が身につき、どんな相手でも冷静に対処できるようになります。試合を重ねることで、自信を持って試合に臨むことができるようになるでしょう。
筆者の体験談
私も小学校、中学校のときはほぼ毎週練習試合、公式試合をしていました。しかし知らないチームと対戦するときは、自分で勝手に苦手意識を持って体が固くなりうまく勝てなかったこともしばしばでした。対戦予定のチームの試合を良くみて、自分なりにどう試合を進めていくかをイメージトレーニングすることで動きも変わってくると思います。
剣道初心者のお悩みあるある解決!Q&A

- Q子どもが剣道を始めたいと言い出しましたが、親の関与はどれくらい必要ですか?
- A
親の関与は、初めのうちは必要です。具体的には防具の準備や送り迎え、練習のサポートなどです。子どもが慣れてくると、親の関与を徐々に減らしてできるだけ一人でさせるようにしていきます。
- Q剣道は運動音痴でもできるようになりますか?体力がないので相手に迷惑をかけないか心配です。
- A
剣道は、運動能力に関係なく誰でも始められます。体力がない場合でも、練習を重ねることで徐々に向上します。自分のペースで無理なく続けることが大切です。
- Q子供が剣道教室に通う予定ですが、指導者やその配偶者に対する慶弔費用が多く心配です。これは普通のことですか?
- A
剣道教室での慶弔費用は、地域や教室によって異なります。事前に他の保護者や指導者に確認し、一般的な範囲内かどうかを確認すると良いでしょう。
- Q幼年用の剣道防具は何歳(何年生)まで使えますか?大きめを買うべきか、ジャストサイズを買うべきか教えてください。
- A
幼年用の防具は、通常小学校低学年まで使用できます。成長を考慮して、少し大きめの サイズを選ぶと良いでしょう。また、部活動によっては防具を貸出してくれるところもあ ります。先輩からのお下がりを使わせてもらうのも良いでしょう。
- Q剣道の防具の洗い方を教えてください。湯船で洗うのが良いですか?石鹸は使います か?乾くのに何日かかりますか?
- A
まず面金(めんがね、面の正面についている金属)を上にしたとき、面金が浸からない 高さまでタライにぬるま湯を入れます。次に漂白剤の入っていない洗剤を多くならないように入れ、防具を湯に浸します。面は面金を上にしてお湯につけます。10分ほどたったら、お湯を入れ替え再度防具を10分間浸す、これを2回繰り返します。その後は風通しの良い場所で陰干ししてください。乾燥には数日かかることもあります。石鹸は洗いにくいので、使用しない方がよいです。
- Q剣道の面と小手にカビが生えました。特に小手の内側にまでカビが浸透しています。濡れ雑巾で拭いて消毒しましたが、これだけで大丈夫でしょうか?
- A
カビの除去には、まず歯ブラシなどでカビを落とし除菌スプレーをかける、またはタライにぬるま湯を入れて10分程度浸して日干しすると良いでしょう。カビがひどい場合は専門のクリーニングを検討してください。
- Q小2の息子が剣道を始めました。袴はいつから自分で着られるようになりますか?
- A
個人差はありますが、小学校低学年のうちに自分で着られるようになることが多いです。着る練習を重ねることで、徐々に自立していきます。
- Q剣道用のメガネは使いやすいですか?視力の悪い人はメガネではなくコンタクトレンズを使うのが一般的ですか?
- A
剣道用のメガネは使いやすいですが、汗をかくとレンズに汗がかかって見えにくくなったりすることがあるので、コンタクトレンズを使用する方が練習しやすいです。
- Q剣道をやる時に前髪をどうしていますか?崩れにくくする方法を教えてください。
- A
剣道をする際には、面タオルを帽子の形にして前髪を上げて被る。または前髪をピンで留める。しっかりと固定することで、試合中も気にせず集中できます。
- Q剣道で面が正しく打てません。上半身と下半身の動作を合わせる方法を教えてくださ
い。 - A
できている人の動作をみて、それをイメージしながら足さばきと同時に腕を振り下ろす ことを意識して何度もやってみましょう。鏡の前で動作を確認しながら練習すると良いでしょう。
- Q中1で剣道部に入りました。相掛かり稽古で意識すること、合い面を当てる方法、同じ技ばかり打っていて良いか教えてください。
- A
相掛かり稽古では、相手の動きをよく観察し、タイミングを合わせることが重要です。合い面を当てるためには、相手の体の中心線にそってまっすぐ打突することを心がけて 下さい。同じ技ばかり打つのではなく、面、小手、胴の打突をバランスよく打突する練 習をすることで、相手に対する対応力が向上します。
- Q剣道の練習で納め刀のタイミングが先生と合わず、自分勝手と言われました。どうすれば良いですか?
- A
納め刀のタイミングは、相手の動きをよく観ながら、合わせることが重要です。なんどか繰り返して合わせましょう。
- Q中学から剣道を始めた女子です。守るためのコツを教えてください。
- A
守るためには、ますは構えの段階で竹刀の先の延長線上が相手の喉元になっているか確認してください。人は竹刀と言えども喉元に何かを突き付けられたら、それだけで威圧感を感じ攻めにくくなるものです。また相手の竹刀の根本を払う事で相手は攻撃ができなくなります。さらに間合いも大事で、一足一刀の間合いから離れることで相手が打突しても届きません。
- Q剣道の練習中に友達の太ももに竹刀が当たってしまい、友達がまだ痛いと言っています。 どう対処すれば良いですか?
- A
まずは友達に謝って、先生や保護者にも相談し、適切な対処を行ってください。また、患部に貼る湿布を用意し、冷やすことで痛みを和らげることができます。もし痛みが続くようであれば、友達に医師の診察を受けるように勧めてください。さらに、今後の練習ではお互いに注意を払い、怪我を防ぐための対策を講じることが大切です。
- Q小1の息子が剣道を習っていますが、動作が遅く、打たれた後に体当たりしてしまいます。どう改善すれば良いですか?
- A
動作のスピードを上げるためには、すり足の練習をはじめとした基本技の反復練習が効果的です。また、打たれた後に体当たりするのは剣道においては意味のない動作で、審判に対しても悪い印象を与えます。体当たりの癖を直すためには、本人が意識するだけではなく、その場その場で先生や保護者の方が注意して癖を直すようにしましょう。
- Q剣道の打突時の発声について、威圧感のある声を出す方法を教えてください。
- A
威圧感のある発声をするためには、お腹から声を出すことが重要です。深呼吸をしてから、腹筋を使って力強く声を出す練習をしましょう。喉から出そうとすると声が枯れてしまいます。
- Q剣道で声が小さくて困っています。お腹から声を出す方法を教えてください。
- A
お腹から声を出すためには、腹式呼吸を練習することが重要です。深呼吸をしてから、 腹筋を使って力強く声を出す練習をしましょう。
- Q剣道で声が小さくて困っています。お腹から声を出す方法を教えてください。
- A
お腹から声を出すためには、腹式呼吸を練習することが重要です。深呼吸をしてから、腹筋を使って力強く声を出す練習をしましょう。
- Q剣道の体力付けについて教えてください。試合でバテないための方法を知りたいです。
- A
体力をつけるためには、ランニングや筋力トレーニングが効果的です。時間がとれなければ準備運動の中で道場内を数周走ることも取り入れてみて下さい。また、試合形式の練習を取り入れることで、実戦での持久力も向上します。
- Q中学生から剣道を始めた初心者ですが、試合での戦略として積極的に打つべきか、間合 いを取るべきか教えてください。
- A
試合では、相手の動きをよく観察し、状況に応じて積極的に打つか、間合いを取るかを判断することが重要です。しかし、初心者の場合は積極的に前に出て打つ経験を積んだ方が良いです。そのことで、はじめはなかなかうまくいかなくても、一本にする打突のタイミングが自然と分かるようになっていくからです。
- Q息子が剣道で強くなるためにはどうすれば良いですか?
- A
基本の練習を日々大事にすること、特に自分の体の中心線にそって素振をする練習を繰り返して下さい。これは鏡などをみてまっすぐ振り上げ、まっずぐ振り下ろすという練習です。斜めに打つ悪い癖がつくとなかなか直らず、試合時にまっすぐ打つ相手より打突が遅れることになります。また試合も沢山経験して反省点をもとに練習をする事が重要です。また、技術だけでなく、精神面の強化も大切です。先生や先輩からのアドバイスを積極的に取り入れましょう。
- Q息子が剣道の試合で勝つためにはどうすれば良いですか?家で素振り以外にできる練習方法を教えてください。
- A
家でできる練習方法としては、体力トレーニングやイメージトレーニングが効果的です。また、試合のビデオを見て戦術を学ぶことも役立ちます。特に準決勝や決勝戦に進出するチームは、参加チームの中でも特に実力が高いので、これをビデオ観察することで多くの学びを得ることができます。試合の流れや選手の動き、試合の進め方などを注意深く見て、自分の練習に取り入れてみてください。
- Q剣道を始めたばかりの中2女子です。全中に行けるくらい強くなるための練習方法や思考を教えてください。
- A
毎日の素振りや基本技の反復練習が重要です。また、試合経験を他の選手より多く積むことで、実戦での対応力が向上します。「剣道で以前より疲れない体を作る」「地区大会で2回戦まで勝ち上がる」などどんなに小さくても良いので自分なりの小さな目標を達成していって下さい。その小さな目標達成の積み重ねが、やがては「全中出場」という大きな目標達成に繋がります。
- Q中1で今年から剣道を始めました。新人戦で勝つための条件や練習方法、袴の正しい着方を教えてください。
- A
<新人戦で勝つためには>勝つための技術というよりも面、小手、胴の基本技を他の新 人さんよりもたくさん練習するということです。まだ基本が身についていない状況で試合 に勝つための技術を覚えようとしても身に付きません。
<袴の正しい着方>まず、袴に両足を入れて袴の前側を持ち、腰に巻きつけます。前側の紐を後ろに回し、腰の後ろで交差させます。前側の紐を前に戻し、腰の前でしっかりと結びます。次に袴の後ろ側を持ち、後ろ側の紐を前に回し、腰の前で結びます。袴の裾を整え、左右の長さが均等になるように調整します。袴の裾が地面に引きずらないように注意してください。最後に袴のひだを整え、見た目が美しくなるようにします。
- Q剣道の試合で勝つためのメンタル強化方法を教えてください。
- A
メンタル強化には、日々の稽古で自信をつけることが重要です。また、試合前にはリラックスするための呼吸法やイメージトレーニングを取り入れると良いでしょう。
- Q息子が剣道部で先輩から暴力を受けています。どう対処すれば良いですか?
- A
まずは息子の話をよく聞き、状況を把握しましょう。その上で、学校や剣道部の顧問に相談し、適切な対応を求めることが大切です。
- Q息子が剣道の稽古でお尻を竹刀で叩かれ痕が残っています。どう対処すれば良いか?
- A
まずは息子の話をよく聞き、状況を把握しましょう。その上で、学校や剣道部の顧問に相談し、適切な対応を求めることが大切です。必要であれば、医師の診断を受けることも検討してください。
- Qおすすめの剣道漫画を教えてください。娘が剣道部に入部し、親としても興味を持ちたいです。
- A
剣道をテーマにした漫画としては、『六三四の剣』『BAMBOO BLADE』や『武士道シックスティーン』などがあります。これらの漫画を通じて、剣道の魅力を親子で楽しんでください。
専門家のインタビュー
専門家のインタビュー これから専門家にインタビューし、皆様に剣道上達のための情報を載せたいと思います。インタビューでは、剣道の技術や戦術、精神面の重要性について、専門家の視点から詳しくお話を伺います。また、日々の練習方法や試合での心構えなど、実践的なアドバイスも提供します。これにより、皆様がより効果的に剣道を学び、上達するためのヒントを得られることを期待しています。どうぞお楽しみに!
まとめ
この記事では、剣道の基本から応用まで、そして試合での勝利を目指すための具体的な方法や、初心者が抱える悩みの解決策まで、幅広く解説してきました。剣道は技術だけでなく、精神面や礼儀作法も非常に重要です。日々の練習を通じて、これらの要素をバランスよく身につけることが、上達への近道です。
この記事では以下の内容をお伝えしました。
剣道の基本的な技術とその習得方法
試合での勝利を目指すための具体的な戦術
昇段審査についての基礎知識
初心者が抱える悩みの解決策
剣道具の選び方とメンテナンス方法
また、専門家のアドバイスや他の選手の技術を学ぶことで、さらに深い理解と技術の向上が期待できます。この記事が、皆様の剣道の道を進む上での一助となれば幸いです。
この記事を書きながら剣道に熱中していた時期のことを思い出します。剣道が色々な面で私自身を育ててくれた、このことへの感謝の念が執筆しながら蘇ってきました。剣道を通じて学んだ忍耐力や集中力、そして礼儀作法は、私の人生において大きな財産となっています。
剣道の稽古は決して楽なものではありませんでしたが、その厳しさの中で得られた達成感や仲間との絆は、今でも私の心に深く刻まれています。試合での勝利や敗北を通じて、勝つことの喜びや負けることの悔しさを知り、それが私の成長の糧となりました。
また、剣道を通じて出会った多くの人々からの教えやアドバイスも、私にとって大きな励みとなりました。彼らの支えがあったからこそ、ここまで続けてこられたのだと感じています。
この記事が、皆様の剣道の道を進む上での一助となれば幸いです。これからも継続して努力し、剣道の魅力をたっぷりと楽しんでください。そして、剣道を通じて得られる多くの学びや経験を、ぜひ大切にしてください。もしこの記事が役に立ったと感じたら、ぜひ友人や仲間と共有してください。そして、さらなる上達を目指して、頑張りましょう!
お問い合わせなどございましたらここをクリックしてください。

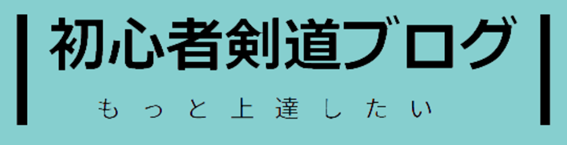

コメント